「心斎橋オーパが閉店」との記事があった。「心斎橋オーパ」は大阪御堂筋沿いにあり「オーパ」のフラッグシップ店舗だと思う。ファッションビルと呼ばれる10~20代をメインターゲットにしてきた商業施設はどんどん姿を消している。
ファッションビルを調べてみると、「衣類や雑貨などファッション関連を取り扱う専門店を主なテナントとするショッピングセンターの一種」とある。近年はターミナル駅にある駅ビルもそのカテゴリーに入っている。諸説あるがファッションビルは西武グループが池袋でスタートさせたと言われている。特に渋谷カルチャーを作った、パルコパート1、2,3、クワトロの4館体制は、街づくりや、ファッショントレンド、若者文化を発信していった。1980年代には「デザイナー&キャラクターブランド」(俗にいうDCブランド)ブームが起こり「ラフォーレ」や「マルイ」を中心に広がっていった。1990年代からは「ギャルブーム」が始まり「渋谷109」は聖地になっていった。
グループでいうと前述した「パルコ」が現在でも一番存在感はある。ネットで見ると現状16店舗(松本が閉店で15になる)となっている。それでも閉店した店も多く、上述した渋谷も3店なくなり、宇都宮や千葉など10店舗程なくなっている。イオン系では「オーパ」が14店舗(心斎橋が閉店で13になる)。オーパもネット上では8店舗程閉店している。同じくイオン系では「フォーラス」は金沢1店舗になっており、好調だった仙台を中心に「オーパ」への業態変更もあり6店舗なくなっている。「ビブレ」は23店舗あったが(東北の別会社を含めると31店)イオングループ下でフォーラス同様「オーパ」への業態変更もあり現状2店舗となっている。かつては各主要都市に必ず1つはファッションビルが存在していた。
20代中心にファッション動向が変化したのだろうか?まずターゲット年令層が大きく減っている。年代層別人口を調べると1995年は15才~29才までの人口が27241(千人)で全体構成比では21.6%を占めていた。それが2023年には人口は18209(千人)で構成比は14.6%まで大きく減ってきている。対象の人口は66.8%まで下がっている。単純にその世代でファッションに興味を持つ比率が同じだとしても、おそらく購買客数は70%以下になっている。
さらにZ世代(2000年前後生まれ)の調査では「ブランドを意識しない」割合が70%超というデータもある。そしてファッションについてはデザイナーブランドのチェックも欠かさないが、購入店舗の上位は「ザラ」「ユニクロ」「GU」「セカンドストリート」となっており、さらに通販のウェイトも上がっている。少し古いが2014年の消費者庁の若者の消費動向調査では、30才未満の1カ月当たりの洋服の平均支出額は1999年度男性5338円女性9345円が、2014年男性2201円女性5081円とほぼ半減するほど大きく下落している。
ターゲット人数が大きく減少し、さらにファッションへの購入金額が減っていく流れの中では当然ファッションビルは成り立ってはいかない。
何とか現状も数字を確保しているファッションビルもある。百貨店と連動してインバウンド客に向けたブランドも展開している「心斎橋パルコ」や大都市ターミナルの駅ビルの「ルミネ」や「アトレ」などは順調な流れのようだ。つまり大きな商圏を持っていることとその立地環境に左右されており、MDそのものよりそれ以外の集客環境のウェイトが高くなっているように感じる。
もう間違いなく、大都市圏以外ではファッションだけで集客できる商業施設は成り立っていない。
■今日のBGM
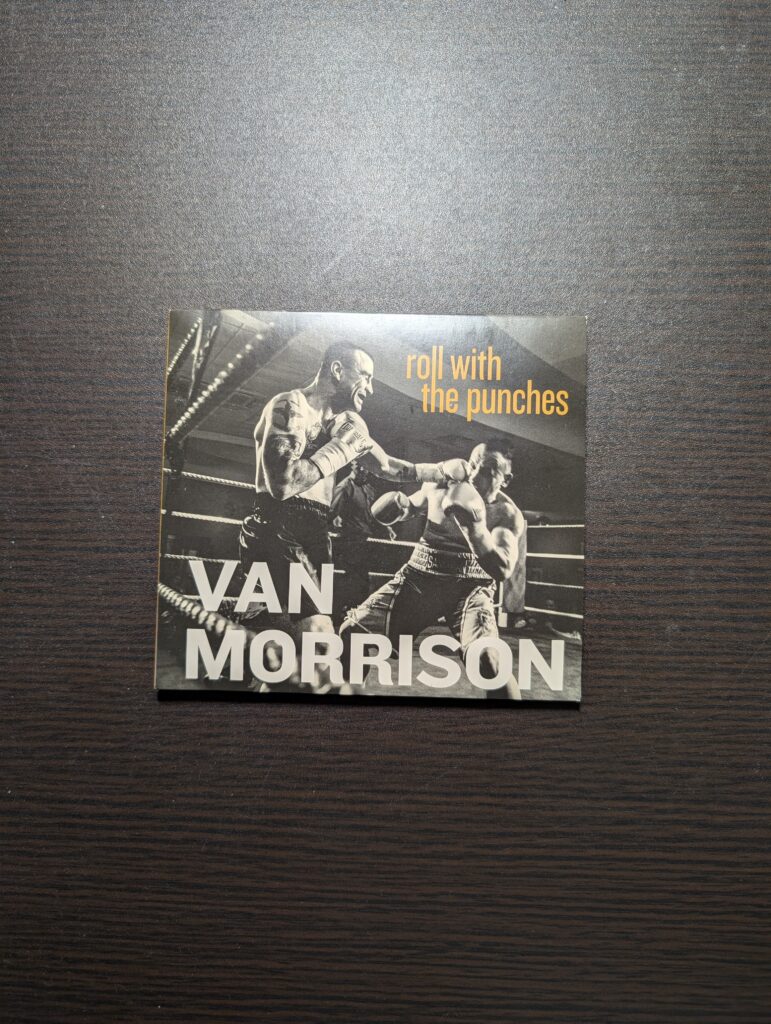
コメントを残す