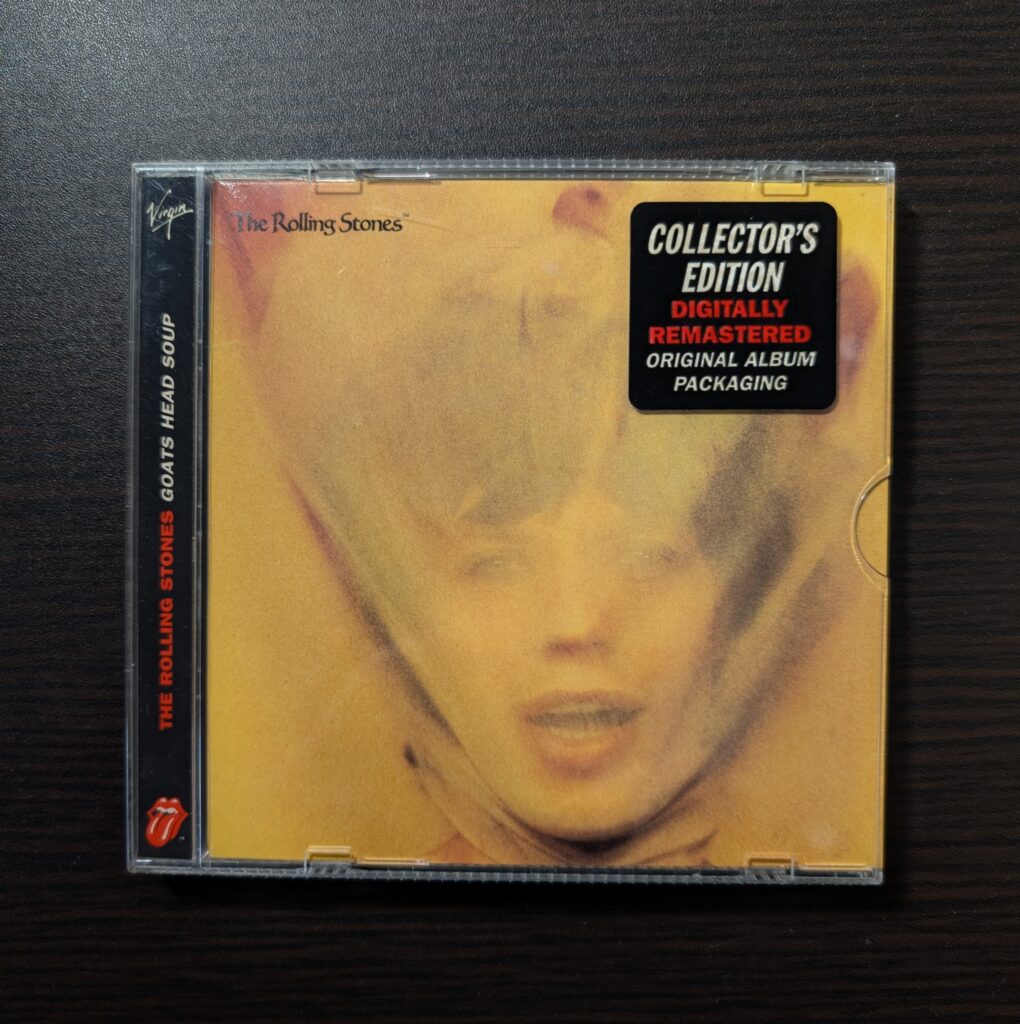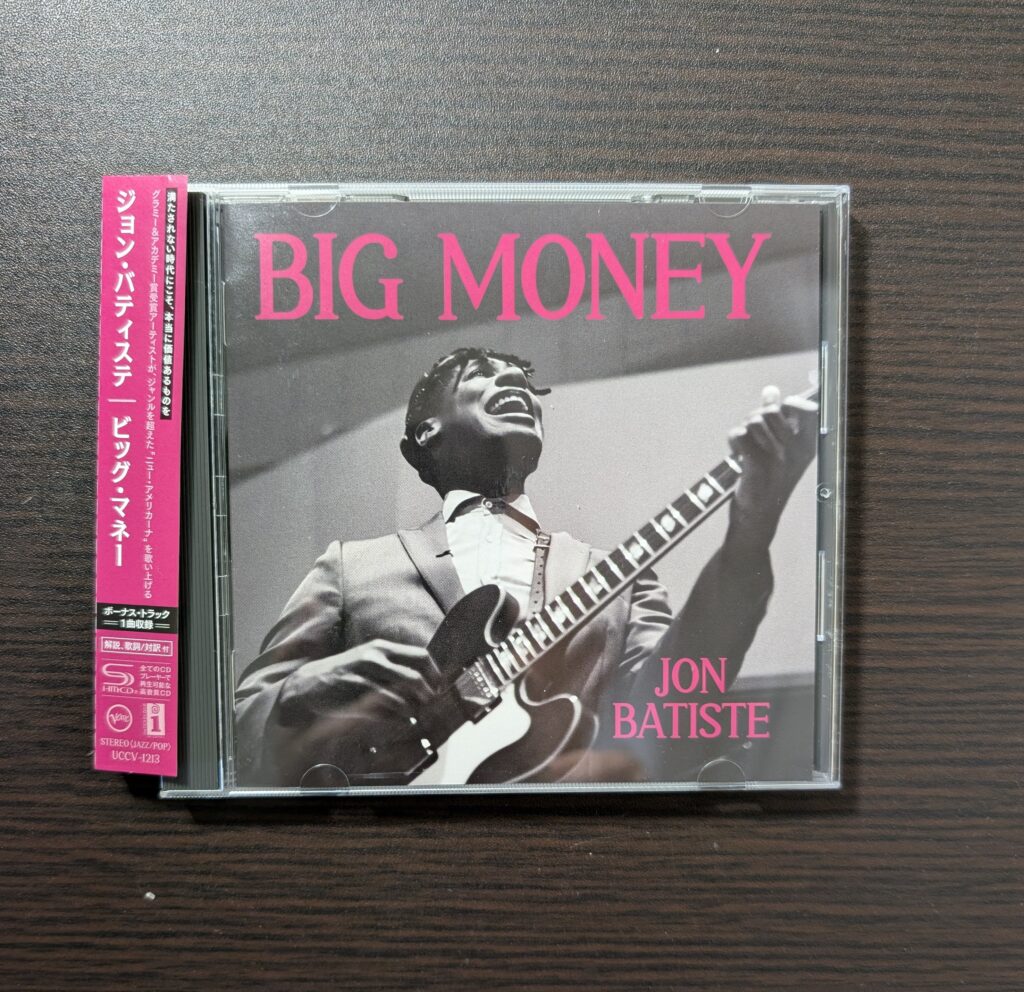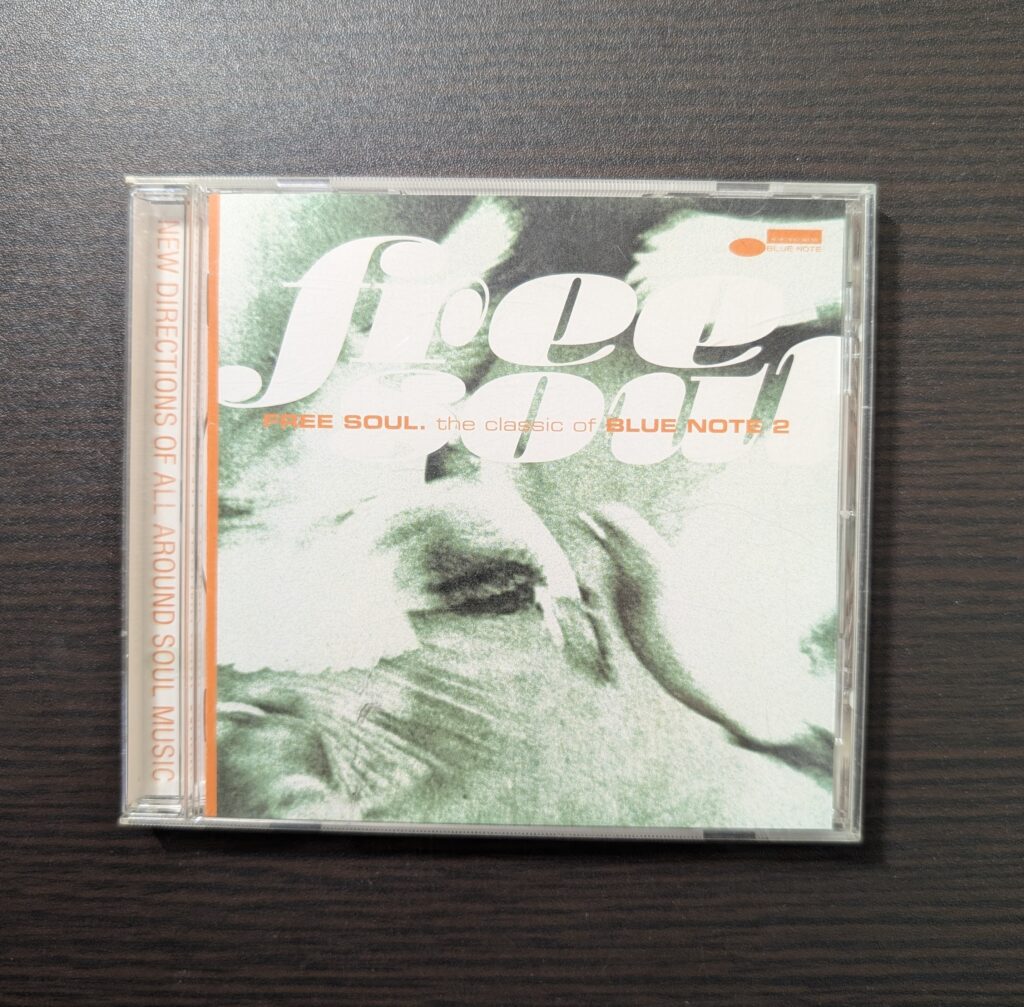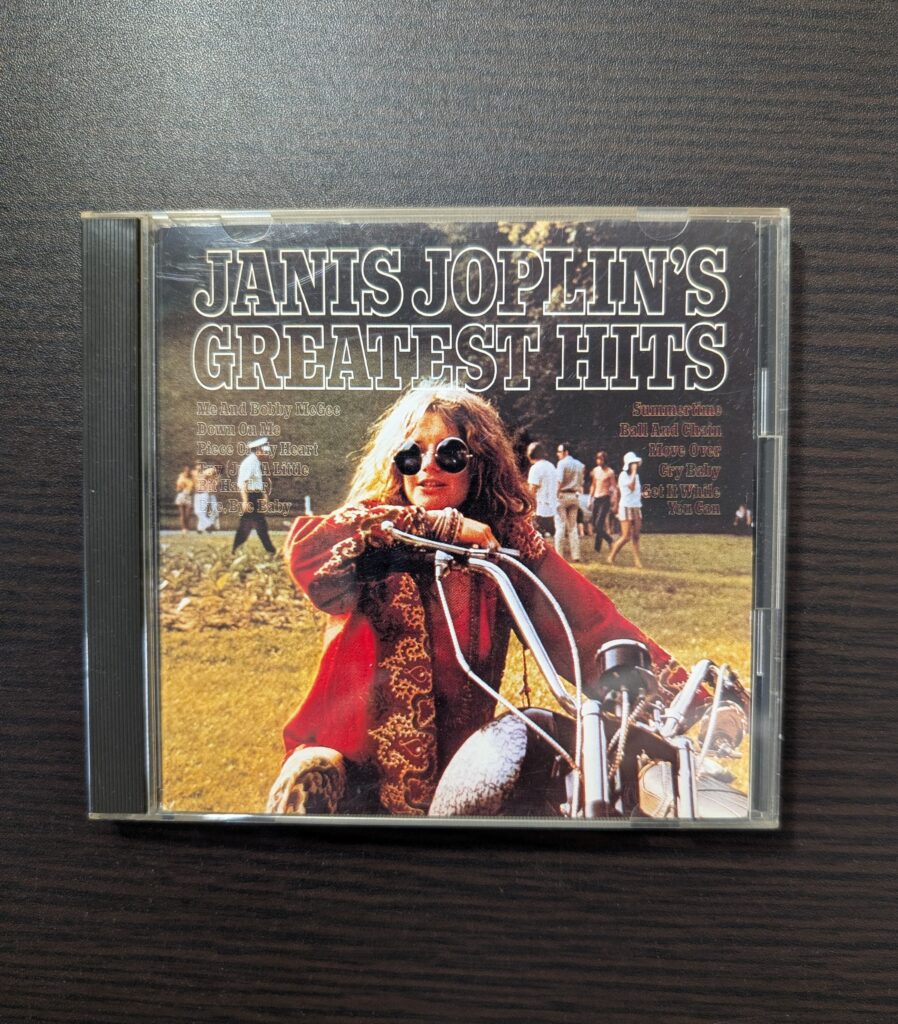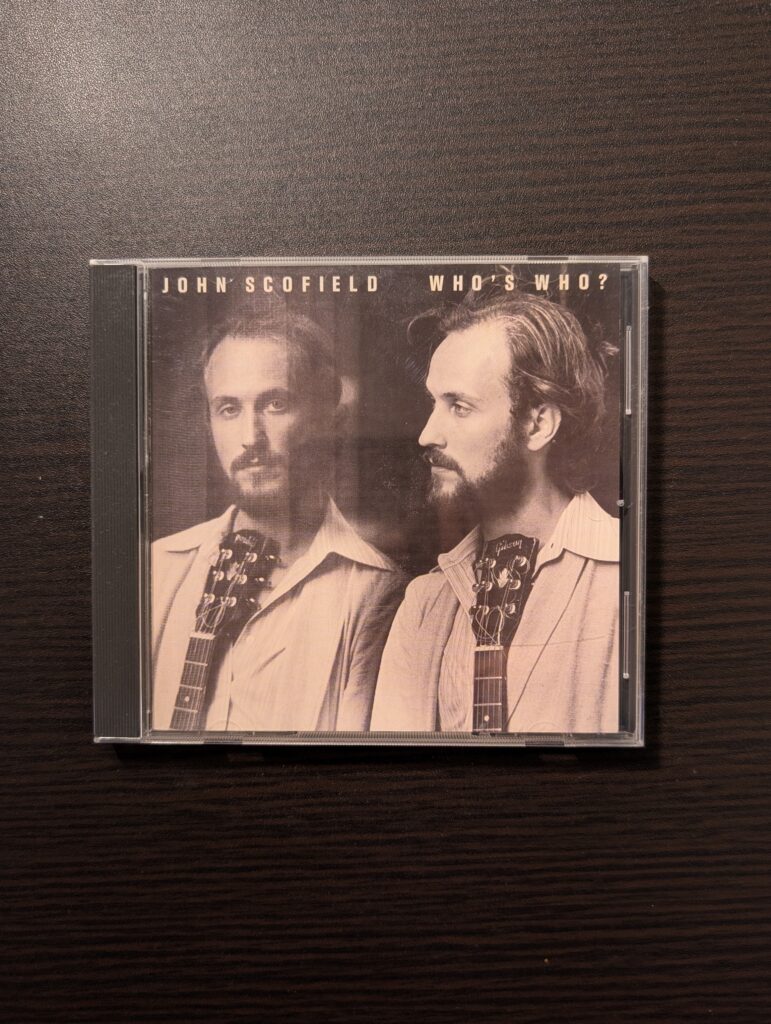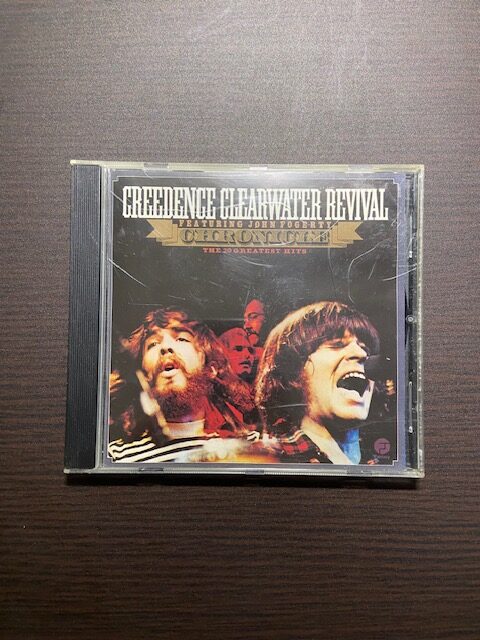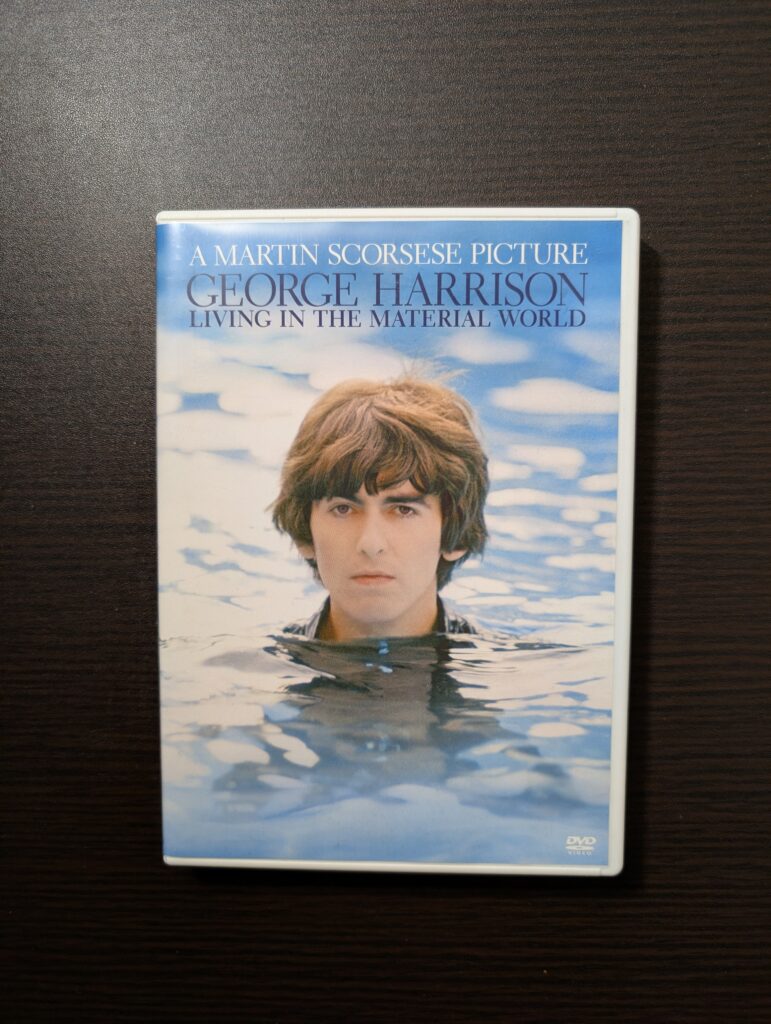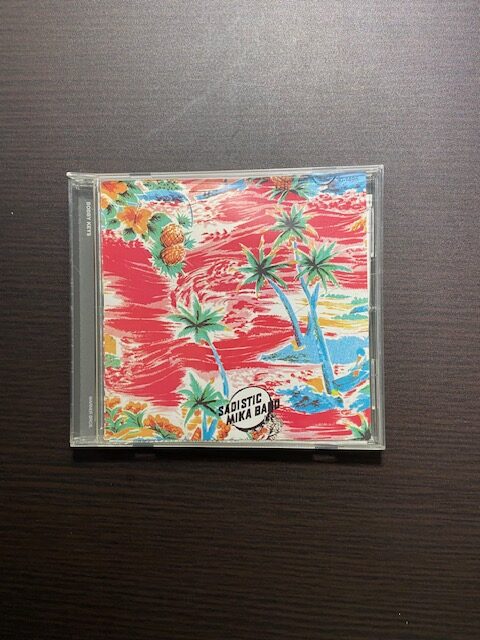福岡は、街や人との相性がすごく良く、個人的には日本で一番いい街だと思っている。四半世紀位前に住んでいたことがある。天神ビブレというファッション中心の商業ビルで店長をさせてもらっていた。もともとはマイカルグループNo1の収益店舗で、在任時は急降下中ではあったがビブレではまだ収益面ではNo1の店ではあった。その話はさておき、天神地区は九州の商業の中心のイメージがあり、大型商業施設がしのぎを削っていた。さらに西通りや親不孝通りにも多くの店があった。でも、毎日毎日飲んでいたことが一番の思い出かもしれない。どの店で飲んでも、親しみがあり安くてうまかった。
ワンビルという巨大施設を見てきた。ビブレとコアと福ビルが1つになっており、19階建てでファッション、ビジネス、ホテルの大きな近代的なビルに生まれ変わっている。商業エリアはがっかり感が強く、「もう行かなくていい」という感想につきる。「シャネル」を誘致するのに力を出し尽くし、テナント揃えがバラバラで、俗にいう人気どころも入っていない。さらに大きなインパクトを残すブランドも少ない。有力テナントが他の商業施設とのつながりが強く、リーシングが難しかったのだとは思う。もうすでに退店ショップもあった。商業だけの売上なら、過去の商業施設の合算の半分以下になっているのではないか?
先日、福岡パルコが建替えのため27年2月に閉店すると発表された。旧岩田屋の物件で好立地ではある。昨年の売上が280億となっている。さらに西側にある新天町の商店街もパルコ跡地と合わせて大規模再開発されると発表されている。再開発まではその売上分も消える。今回ぶらぶら街を歩いていて、パルコ→新天町→岩田屋→ソラリア→(三越食品)→地下街の人の流れが多く、渡辺通りをはさんだワンビルとは客数も客層も違っていた。これでパルコ、新天町商店街がなくなればお客様の流れは大きく変わるかもしれない。百貨店顧客中心になり、九州各地から集まっていたヤング層の行くところはなくなってしまう。
その後博多駅周辺に行ったが、賑わいは間違いなく天神地区から移ってきている。以前も書いたかもしれないが可能であれば、阪急が増床(マルイを阪急メンズ館にできないか?)すれば、岩田屋の売上を超えることもあるのではないかと思う。ちなみに、現状博多阪急の売上は700億弱くらいで、博多大丸、三越よりも売上は大きい。キャナルシティと組んでその間の地域を活性化させ人気店を点在させれば、2核体制で1つの商業地域が出来上がり、天神から若い客層が移ってくるかもしれない。そうすれば駅近辺の商業面積の問題も解消されるし、天神との位置づけも間違いなく逆転する。
天神は「商業の街」だった。今回の天神地区の再開発は「ビジネスの街」への移行の意思が強い。果たして成功するのだろうか?ハコは大きなきれいなものを作ったし、さらに計画されている。そして、そこに入る企業は来るのだろうか?先行したワンビルの入居率は現在80%と報道されている。
街と人が良かった天神が変化して、その良さが薄れていくような気がする。
・追記
博多のホテルの値段が非常に吊り上がっている。今回ネットで探したが、博多⇔天神間のビジネスホテル(カプセルは除く)で最安値が1泊15000円だった。ちなみに前日は大阪淀屋橋近辺に止まったが、10000円以下のホテルは数か所あった。中国の春節の時期だからかもしれないが、どのホテルも4~5年前と比べても倍以上になっているような気がする。この値段では普通のサラリーマンだと仕事でつかえないのではないか。リッツカールトンの客が屋台で飲む絵は見えない。
■奥がワンビル(天神ビブレ跡)、手前は開発中のビル(天神ビブレ2跡)